新潟バイパスがすごい。信号ないし80キロ制限でもはや無料の高速道路

新潟市民にとっては新潟バイパスは当たり前にある道路。
無料で走れる準高速道路みたいな扱いで、もはや生活に欠かせない交通インフラです。
実はこのバイパス、全国的に見ても珍しい凄いバイパスだってご存知でしたか?
それをこの記事でご紹介して行きたいと思います。
新潟バイパスと、一本道続きである新新バイパス・新潟西バイパスの区間がどこまでか、制限速度は何キロか、他にも知らないとちょっと困ったことになる注意点なども解説しますね。
他にも栗ノ木バイパス、新津バイパスなどたくさんありますが、今回は新潟バイパスとその延長線の道路にしぼった話です。
交通量がすごい
新潟バイパス・新潟西バイパス・新新バイパスの交通量は凄いんです。
全国の一般道の交通量調査で、なんとトップ10に新潟市内が観測地点が3か所もランクイン。2位、
しかも1位の横浜との差は誤差のレベルで、あわや全国1位を取ってしまうところでした。
これについては単独で記事にしているので、詳しいことはそちらで。
長さがすごい
新潟西バイパス・新潟バイパス・新新バイパスの3つを合わせた距離は約37kmあるのですが、その間ずっと信号が1つもありません。しかも高速道路みたいな高架道路です。
これだけの長い距離の高架で信号がないバイパスは、全国的にも少ないらしいです。
新潟のバイパス事情は全国でもトップレベルだと思うと何だか誇らしい気がしてきます。
その代わり、交通量も全国屈指で、一般道のみの交通量調査でトップ10に3か所もランクインしています。その3か所がすべてこの新潟バイパスです。
新潟市の交通量の凄まじさについて詳しいことはこちらの記事にて。
信号がないのがすごい
距離がめちゃめちゃ長いのに、その間信号がないんです。
制限速度が80キロなのがすごい
なんとこの新潟バイパス、一般道にもかかわらず80km/h制限があるんです。
凄いですよね。
県外の方が聞いたらビックリじゃないですか?
他県にもそういう道路ってそうそうあるんですかね。
パーキングエリアがあるのがすごい
新新バイパスの豊栄ICから少しだけ新発田方面(東方面)に進んだところに、なんとパーキングエリアがあります。
こうなるともはや高速道路。
高速のサービスエリアよろしく、うどんやそばに豚骨ラーメン、スーラータン麺、かつ丼、牛丼、カレーライスにオムハヤシと、定食屋並みのラインナップ。
さらにはホットドックにジャンボフランク、たこ焼きなど軽食もカバー。
新潟バイパス・新新バイパス・新潟西バイパスの区間
話をしやすくするために、各バイパスがどこまでなのか区間を先にご説明しておきます。
新潟市でバイパスと言ったら、あの西区~新発田までの一本道全体が新潟バイパスかと思ってしまいますが、実は以下の3つの区間に分かれてます。
西側から順に、
| 区間 | 長さ | およその制限速度 | |
|---|---|---|---|
| 新潟西バイパス | 曽和IC~黒埼IC | 8.6km | 80km/h |
| 新潟バイパス | 黒埼IC~海老ケ瀬IC | 11.2km | 70km/h |
| 新新バイパス | 海老ケ瀬IC~新発田IC | 17.2km | 70km/h |
制限速度は一部60km/h、50km/h制限の区間があります。
曽和はICというより単なる交差点ですが、ICと呼んでおきます。
ちなみに、曽和ICより西側(巻方面)はバイパスという名称ではなく、新潟西道路と呼ばれ、明田交差点という場所までを指します。
余談ですが、上の3つのバイパスに新潟西道路をあわせた、新潟東西道路という呼び名もあったりします。
これら3バイパスに存在するインター1つ1つと、制限速度がどこからどこまでが何キロかなど、詳しいことは以下の記事にまとめています。ご興味があればご覧ください。
注意点
新潟・新潟西・新新バイパスは非常に便利な道路である一方、時おりトラップというか、わかってないと意図しないことが起きるので要注意。ぜひ把握しておきましょう。
- 左車線を走ってるとそのまま下りる
- 左車線から右方向へ乗る(紫竹山、黒埼)
- 紫竹山IC:出口が2個ある(西方面・東方面ともに)
- 弁天IC:東方向へは乗降不可
- 逢谷内IC:東方向へは乗降不可
- 高山IC:西方向へは乗降不可
- インター下り損ねるとタイムロス大
などなど。
これらは、ハッキリ言って元々知ってないと容易にトラップにかかってしまいます。初めて走る場合やバイパスに乗り慣れていないなどの場合、かなりの確率でトラップにかかりやすいです。
自分でもビックリですが、僕はわかっているのにたまに間違えます。ボーっと左車線走ってるといつの間にか下りちゃってるんです。
以下の記事に新潟バイパスにありがちなトラップや注意点、対処方法などをまとめておきました。バイパスの運転に不安がある場合はどうぞ。
バイパスばかりが能じゃない
バイパスは確かに便利なんだけど、それはバイパスに乗ってからの話。
日中の新潟市中心部はいたる所で渋滞発生。
インターによっては、そこに至る大通りが混んでいることがあり、時間帯によってはバイパスに乗るまでに結構時間かかったり。
「バイパス乗るのにこんなに時間かかるんだったら、普通の道で行けばよかった」と後悔することが時おりあります。
バイパスがもうすぐ近くなら良いですが、ちょっと距離がある時は、他に良い道が近くにないか考えてみると良いかもしれません。。
たとえば、以下の道。
- 海沿い402号線
- 信濃川沿い右岸(本川大橋~万代島)
- 信濃川沿い左岸(下町~関屋)
- 西川沿いの道
- 三条小須戸線(県道1号線)
- 曽野木一日市線(県道290号線)
- 千歳大橋付近~駅南への裏ルート
- 竹尾交差点~イオン新潟東・松崎エリア
これらの道は、信号が少なかったり、空いてる事が多かったりと、バイパスには遠く及ばないながら、移動時間の短縮とストレス軽減など快適なドライビングタイムに貢献してくれる優秀な道です。
バイパスで移動できる距離が長いときは短縮できる時間が大きいため、たどり着くまでに多少時間を要してもバイパスを利用すべきかもしれません。
たとえば、西区の小新インター付近のイオン新潟西から、東区の逢谷内インター付近のイオン新潟東まで行くとか。
バイパスで走れる距離が短いときは無理に使わず、上記の道を使ってみることもご検討ください。
詳しいことは以下の記事で解説しています。
まとめ
新潟バイパス・新潟西バイパス・新新バイパスがいかに凄いかを解説させていただきました。
この3バイパスは新潟市を東西に走る交通の冠動脈なので上手に使えば新潟市内の移動の時短にもつながります。
新潟は電車やバスの交通機関が乏しく、必然的に自家用車での移動の比重が高い車社会となっています。
ぜひとも3バイパスの特徴を把握して、新潟でのカーライフを充実させてください♪
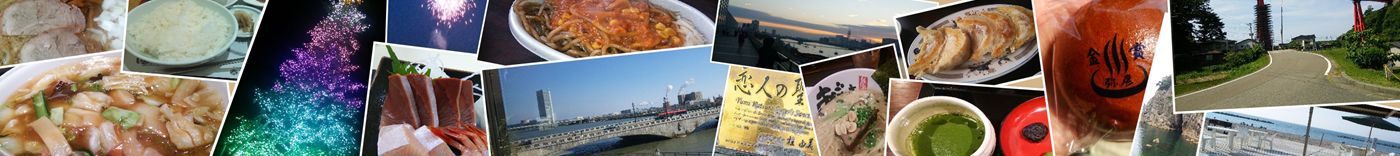














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません