新潟バイパスは怖くない。事故を未然に防ぐための注意点まとめ
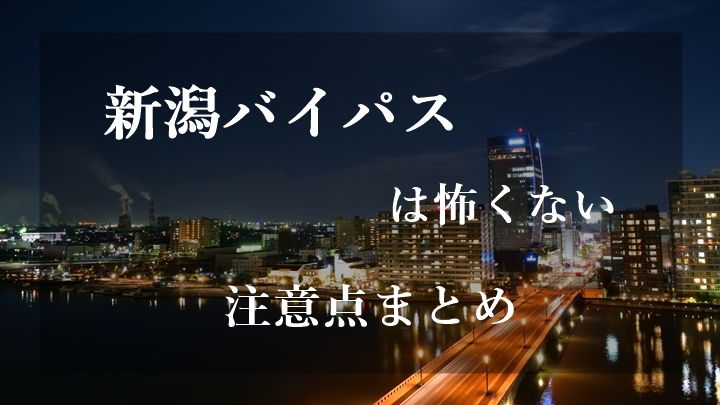
新潟バイパス・新潟西バイパス・新新バイパスは車社会の新潟市では欠かせない道路で、存在感は高速道路並み。
信号がなくスピードも60キロ以上出せる、とても便利な道路なのですがその反面、普通の一般道とは少し違い注意点もあります。
- いつの間にかバイパスを下りてしまう
- 出口が2つあるインターはどっちに進めば良いか謎
など、バイパス初心者や慣れていない人を不安にさせます。
今回は、新潟バイパスで起こりえる幾つかのトラップというか複雑な部分の対処法を解説したいと思います。
左車線を走ってるとそのまま下りる
新潟バイパスは片道2~3車線ある幅員の広い道路ですが、一番左の車線を走ってるとそのままインターを下りてしまうことがあります。
でも気づいた時には下り口にさしかかっていて、でも右の車線は車がいっぱい。車線変更できずにそのままバイパスを下りることに。
目的のインターより早く下りてしまい、せっかくバイパスに乗ったのに、時間のかかる下道をより多く走ることになり、余計なタイムロス発生。
でも、そのようなインターは少なく、僕が数えた限り新潟バイパス・新潟西バイパス・新新バイパス全体でも5つのインターだけ。
- 小新インター西進行
- 黒埼インター西進行
- 女池インター東進行・西進行
- 竹尾インター東進行・西進行
- 海老ケ瀬インター東進行
ここで言う西進行とは、西(曽和インター方向)に向かって、東進行とは、東(新発田インター方向)に向かって走っている時という意味です。
例えば小新IC。
西進行(曽和ICへ向かう)のときは一番左車線がそのまま下り口になります。
東進行(新発田ICへ向かう方向)のときは、こうではなく、下り口へ向かう車線が現れます。
左車線から右方向へ乗るインターがある(紫竹山、黒埼)
通常、乗り口は、
- 左方向へは一番左の車線から
- 右方向へは一番右の車線から
となっています。
それが、黒埼IC・紫竹山ICは、どっちの方向に乗るにしても左側になります。
例えば紫竹山インター。
新発田IC方面への乗り口が手前。道路と標識で赤色で示されてます。
さらに進むと、曽和IC方面への乗り口。緑色で示されてます。
色分けをたよりに進むと、まあまあわかりやすいです。
紫竹山IC:出口が2個ある(西方面・東方面ともに)
紫竹山インターは出口が2個あります。
1つはバイパスから下道に下りる出口、
もう1つは、亀田バイパスにつながるという、高速道路のジャンクションのようになっています。
東へ向かって(新発田IC方面へ)走ってるときは、
- 1つめ:下り口
- 2つめ:亀田バイパスへ
西へ向かって(曽和IC方面へ)走ってる時は、
- 1つめ:亀田バイパス
- 2つめ:下り口
となっています。両方向で1つめ、2つめが逆なのでご注意を。同じだったら覚えやすいのに、残念ながら逆なんですよ。
一方向にしか乗降できないハーフインターがある
ハーフインターなどと呼ばれるようですが、東方面(新発田IC方面)・西方面(曽和IC方面)のどちらか側にしか乗り口・下り口がないインターが存在します。
高山IC:東方面のみ乗降可能
弁天IC:西方面のみ乗降可能
逢谷内IC:西方面のみ乗降可能
これで何が困るかというと、本当は弁天インターの先の紫竹山ICで下りるつもりだったのに、間違えて手前の弁天ICで下りてしまったとき。
バイパスは普通、下りてしまっても直進すればまた同じインターからすぐ上がれます。しかし、ハーフインターでは乗り口がなくそれができません。
向かい側にある道は、バイパスの乗り口ではなく側道です。
インター下り損ねるとタイムロス大
もう1つよくあるのが、たとえば弁天で下りるつもりが通り過ぎたとき。
通り過ぎるときに「あ、いま弁天インターだった!」と気づき、慌てて紫竹山インターで下りる。
そしてまた紫竹山インターから乗って弁天で下りようとしたら、弁天はハーフインターでこっちがからは下りられない。仕方なく1つ向こうの桜木インターで下りて・・・という悪循環が生じ、もうどうしようもありません。
僕これ何度か体験しました(汗)
ボーっとしてるといつの間にか下りるべきインター過ぎてるのは新潟バイパスあるあるです。
このように、間違えて下りるとやっかいです。
弁天・紫竹山の周囲は時間帯によってかなり混むし、道が複雑なのでかなりタイムロスします。ご注意ください。
新潟バイパス初心者の心得
新潟バイパスによくあるトラップをまとめてきました。
最後に、新潟バイパスをあまり走ったことがなく慣れていない、インターのクセをあまり把握できていないなどの場合、特に注意した方がよいと思われる点だけピックアップしてまとめておきます。
- 事前に利用するICを調べておこう
- 右車線ではなく真ん中・左車線を走ろう
- 短い距離は下道で
事前に利用するICを調べておこう
ここまでにご紹介したバイパスで起きやすいトラップも、乗り降りするインターのことを把握できていれば避けられる事です。
ようは知らないから引っかかってしまうトラップ。
長年、新潟バイパスを利用しまくってあらゆるインターの様子が頭に入っていれば大丈夫ですが、そうでなければ事前に下調べしておきましょう。
幸いなことに、今はGoogleマップという超便利なものがあります。
航空写真の地図を見て、実際の道路の形状を確認できます。
拡大してよく見れば、「女池ICでは左車線を走ってると下りることになるな」などと分かります。ぜひご活用ください。
また、「〇〇IC」などと標識が道路左側に出ていて次のインターがわかるけど、車が連なってると中々左車線に入れないことがあります。そのうち下りるべきインターが近づいてきて焦ったり。
こういうのは危険だしストレスになるし、あおり運転の罰則が強化された現在、多少でも強引な車線変更はよした方が無難。
事前に、下りるインター付近だけで良いのでインターの順番を記憶しておきましょう。
そうすれば、「いま女池ICだから、次の次が弁天ICだ」など、あとどれくらいかわかります。
そしたら、女池を過ぎたら余裕を持って左側車線に寄っておけます。桜木を過ぎて「つぎは弁天IC」という標識で気付いても、道が混んでると左車線による暇がないかもしれません。
下りるインターの2個前のインターを過ぎた辺りで、左車線に寄ろうとする位が無難です。
女池インターなど左車線は下りてしまうトラップにかかるのでそれも気を付けつつ。
右車線ではなく真ん中・左車線を走ろう
基本的にいつも真ん中車線を走りましょう。
片側2車線の道では左側車線を。
一番右の車線は、全車線の中で比較的スピードを出してる車が走ってます。後ろからあおられ気味になって慌ててもいけません。
また、「気づいたら次が下りるインターだった」という際も、最右車線より、中央車線にいたら左車線に寄りやすいですしね。
なるべく最右車線は走らないようにすることが、バイパスでの安全につながります。
短い距離は下道で
バイパスのインター1、2個分くらいなら無理にバイパスに乗らず下道で行った方が早いか、ほとんど変わらないことも多いです。
たとえば、デッキィ401からアピタ新潟西店に移動したいとします。
バイパスで行こうとしたら、女池ICから乗って黒埼ICで下りることになります。
インター1つ分ですが、それなりに距離があります。
でも、下道で行ってもあんまり変わらなそうです。
Googleマップのナビでもルートはバイパス以外にも出てきます。
時間帯による下道・バイパスの混み具合や好みにもよるかもしれませんが、無理にバイパスを使わなくても良い場面もあります。
ゆくゆくは、状況によって上手に使い分けられるようになることを目指しましょう。
色んな道を覚えてくると便利になります。
知ってると便利な道は、以下の記事が役立つと思います。
まとめ
新潟バイパスのトラップや注意点、その対策方法をまとめました。
- 左車線を走ってるとそのまま下りる
- 左車線から右方向へ乗るインターがある(紫竹山・黒埼)
- 紫竹山ICは出口が2個ある(西方面・東方面ともに)
- 一方向にしか乗降できないハーフインターがある
- インター下り損ねるとタイムロス大
新潟バイパスに慣れていない場合の対策は、
- 事前に利用するICを調べておく
- 右車線ではなく中央車線・左車線を走ろう
- 短い距離なら無理にバイパスではなく下道で
でした。
新潟バイパスを上手に使って移動時間を短縮して快適なカーライフをお過ごしください。
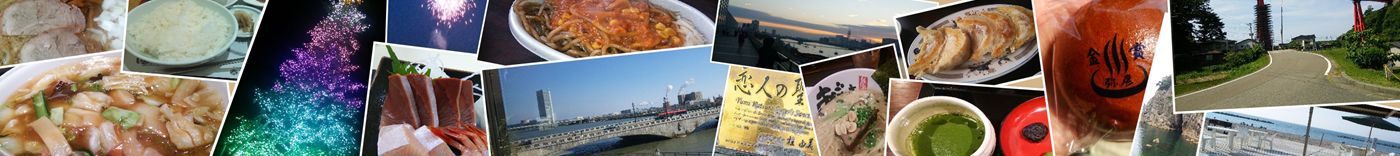












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません