新潟市でマイナンバーカードを申請する方法まとめ
新潟市のマイナンバー申請が始まる

この記事は早い段階でマイナンバーカードの作成方法を調べてまとめた簡易版です。
のちに実際に私が中央区役所でマイナンバーカードを作成し、その時のことを例に1つ1つごやり方を説明した完全版が別にあるのでご覧ください。
マイナンバーカードの申請は新潟市はのびのびになっていましが、ついに開始されました。
僕も当初は、「何でこんなもの作る必要があるんだ、ややこしい」と思っていたのですが、調べてみたら作っておくことで色んなメリットが受けられることを知り、作った次第です。
よくわからなくて不安だから・・・と思って放置するのは勿体ないレベルです。
ちゃんと理解しておいて、必要なときに利用できれば大幅な時間短縮や労力の節約につながるんです。
たとえば、わかりやすいのが、コンビニで住民票の写しなどが取れる事です。
これだけでもすごく便利になります(むしろ今までのシステムが時代に合ってなかった気が・・・)
また、申請から届くまでに1か月ほどかかるとの事なので、申請は早めに行う方が良いでしょう。
という事で、ここで1度マイナンバーカードの申請方法や、マイナンバーの事について振り返ろうと思います。
まずはマイナンバーカードがどんな物だったか、さっと振り返ります。
私が実際マイナンバーカードを申請して受け取った体験談はこちらの記事に詳しく書いてます。
そもそもマイナンバーカードって?
そもそもマイナンバーが何だったか。今一度おさらいします。
日本国内に住民登録があるすべての人が持つもので、大人でも子供でも全員です
顔写真付きICカードで、12桁です。一生変わりません。
マイナンバーカードは表に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、
裏にマイナンバーが記載されています。
そして本人確認、身分証として使えます。
超便利なカードです。
取得するか否かは個人の任意です。別に取得しなくてもOK。
マイナンバーは、住民票の写しなどに記載する事が出来ます。
記載する意味は、行政の手続きによってはマイナンバーが記載された住民票の写しが必要な物があり(難病の申請など)、そのために記載します。
ちなみに、マイナンバーの記載が必要な手続きは新潟市のサイトに記載されています。
マイナンバーカードと、マイナンバー通知カードって違うの?!
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
この2つは別の物です。
マイナンバー通知カードはただの紙のカードであり、マイナンバーと個人情報が記載されているのみで、確認が出来るだけ。
それに対し、マイナンバーカードはプラスチック製で、顔写真と個人情報が一緒に記載されいて、身分証の役割も果たします。
ICカードであり、機械で使ったりする事が出来るので、マイナンバーの確認のみならず、色んな便利な使い方が出来ます。
コンビニで住民票の写しを取るには、このマイナンバーカードが必要になります。通知カードの方では出来ません。
平成27年10月から、マイナンバー通知カードの送付が始まりまして、世帯主宛てに世帯全員分が送付されています。
「え、通知カードなんて見当たらない」という方は今一度探しておきましょう。全国民がどちらか一方を持っている筈のものです。
どうしても見当たらなければ再発行も出来ます。
お住まいの区の、区役所の区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)へお問い合わせください。
マイナンバーカードが持つ6つのメリット
まずはマイナンバーカードを持つ事で得られるメリットについてです。
メリット1:マイナンバーの確認が出来る
これは説明するまでもなく、当然というかマイナンバーカードの最低限の役割です。
メリット2:各種の行政手続きのオンライン申請に利用できる
通知カードの状態ではなく、ICカードであるマイナンバーカードにすることで、e-TAXなどのオンライン手続きに使えるようになります。
市・区役所は平日の17:00頃までがほとんどですから、平日お仕事の方は仕事を休んだり抜けたりしないと行けなくて非常に不便です。
それが今後はものによっては家にいながら、オンラインで出来る事になり、とっても楽です。
メリット3:身分証として使える
マイナンバーカードは身分証として使えます。運転免許証をお持ちでない方もマイナンバーカードがあれば簡単に身分証を持つ事が出来ます。
マイナンバーの確認と身分証の役割がマイナンバーカード1枚で果たせるわけです。
メリット4:オンラインバンキングなど、各種の民間のオンライン処理が出来る
民間のオンライン手続きに利用されます。私たちの身近では、まずは銀行でしょう。インターネット上で振込みなどが行えます。
マイナンバーにより個人が特定できるので、本人確認が容易になります。
今までネットバンクや証券に口座を開くには、ネットまたは書類に色々入力して、本人確認書類を郵送するか、写メで撮って送付するなど、何段階もの手続きが必要でしたが、今後はグッと楽になる事が期待されます。
メリット5:種々のサービスごとのカードが1枚に統合される
全国の市区町村や国が提供するサービスごとに存在したカードが、マイナンバーカード1枚に統合する事ができ、何枚も持ち歩かなくて済むようになります。
それらのカードは市区町村により異なるのでしょうし、必ずしも全てが1枚に統合されるわけではないかもしれませんが、現状よりはマシなはず。
今後の動向に期待大です。
イメージとしては、ドラッグストアとか色んなお店のポイントカードが1枚になるみたいな感じですかね。ちょっと違うかな。まあとにかく枚数が減らせるという事です。
メリット6:コンビニで住民票の写しなどが取れる
2018/3/1から、コンビニのキオスク端末で住民票の写しなどが取れます。
差し当ってすぐ私たちにとってメリットとなるのがこれでしょう。
- 新潟市に住民登録がある(これは当たり前)
- マイナンバーカードを持っている
この2つが利用するために必要な事だそうです。
マイナンバーカードが必要な事以外に、「新潟市に住民登録がある」事が条件とされています。
例えば、お仕事や学校で東京都文京区に住民票がある方が、新潟市の実家に帰省中に新潟市のコンビニで住民票のお写しを取る、などは出来ないという事でしょう。
そして、マイナンバーの通知カードでは利用出来ないのでお気をつけを。
コンビニで取得できるようになる書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の全部(個人)事項証明書(本籍地が新潟市の方のみ)
- 戸籍の附票の写し(本籍地が新潟市の方のみ)
とりあえず住民票の写しと印鑑証明が取れる事は大きいですね。
利用可能時間
朝6:30~23:00となってます。
仕事に行く前や仕事が終わって遅くなっても23:00まではコンビニによって書類が取れるのはかなり助かりますよね。
利用出来るコンビニ
- セブンイレブン
- ローソン
- サークルK
- ファミリーマート
- セーブオン
とりあえず全国区の主要なコンビニは網羅していますね。
コンビニにあるキオスク端末というのを使います。
コピー機の近くに置いてあるもう1つのあれですね。
ローソンだと「Loppi」、ファミマだと「ファミポート」がそれに当たるんだと思います。
キオスク端末が置されていないコンビニはあんまり見た事ないですよね。
とりあえずセブンイレブンとローソン、ファミマ辺りも大丈夫そうな気がします。
セーブオンはどうなんでしょう・・・。
いつから?
2018年3月1日から利用可能になりました。
土日祝もOK。
マイナンバーカードは、申請してから届くまで1か月くらいかかるとの事なので、3/1から使える状態にしておくには1月中くらいまでに申請しておくのが無難そうです。
マイナンバー入手の流れ(申請から受け取りまで)
ではでは、申請して実際受け取るまでの方法を確認していきましょう。
マイナンバーカード申請の流れ
- 申請する
- 1か月ほど待つ
- 交付通知書(ハガキ)が届く
- 必要な物を持ってハガキに記載の交付場所へ本人が取りに行く
- 取りに行った窓口で暗証番号を登録し、マイナンバーカードを受け取る
という流れになります。では1つ1つ詳しくご説明して行きます。
1.マイナンバーカードの申請方法
以下の4種類の方法があります。
- 郵送
- パソコン
- スマートフォン(インターネットまたは、QRコード利用)
- スピード証明写真機(QRコード利用)
QRコードを利用してスマホかスピード証明写真機で申請する方法があるのですが、通知カードが送付された後に引っ越した場合は使えなくなります(インターネットを利用したスマホでの申請は出来ます。)
スピード証明写真機でマイナンバーカードの申請が出来るのは以下の機種のみです。
- 株式会社DNPフォトイメージングジャパン
- 日本オート・フォート株式会社
- 富士フィルム株式会社
QRコードでの申請はここでは割愛させて頂きます。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
通知カードと一緒に封筒に入ってた交付申請書を郵送
通知カードが送られて来た時に、以下が同封されています。
- 「個人番号カード交付申請書」兼「電子証明書発行申請書」
- 送付用封筒
「個人番号カード交付申請書」兼「電子証明書発行申請書」に必要事項を記載し、顔写真を貼り付けて、「送付用封筒」で郵送します。
送付用封筒の差出有効期間が平成29年10月4日までとなっていても、平成31年5月31日までは切ってを貼らずに使えます。
また、無くしたり引っ越した場合は、区役所で新たにもらうか、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードして印刷する必要があります。
申請書と送付用封筒の両方が印刷出来ます。
申請書の書き方も上記のマイナンバーカード総合サイトの同じページに記載されています。
パソコンやスマートフォンで、インターネットから申請
パソコン用の申請ページから必要事項を入力して申請を行います。
通知カードと一緒に郵送されてきた交付申請書に記載されている申請書IDが必要です。
紛失や引っ越した場合は、区役所に行って新たに申請書を貰い、そこに記載された申請書IDをインターネット上で入力する必要があります。
市区町村によっては申請書IDが記載されていない用紙を配布される場合があり、その場合は郵送で申請するしかないようです。
パソコンでの申請方法の詳しい手順はマイナンバーカード総合サイトに記載されています。
2.1か月ほどまつ
申請したら、あとは出来上がるのを待ちます。
申請に不備がなければ1か月くらいとの事です。
3.交付通知書(ハガキ)届く
マイナンバーカードが出来上がると交付通知書のハガキが届きます。
交付場所はハガキに記載されているとの事で、事前にはわからないみたいですね。
4.マイナンバーカードを取りに行く
必要な物を持って、交付通知書(ハガキ)に記載された交付場所に本人が取りに行きます。
必要な物とは以下です。
- 交付通知書(ハガキ)
- マイナンバー通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
やむを得ない事情で本人が受け取りに行けない場合、代理人による受取が可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
5.暗証番号を登録しマイナンバーカードを受け取る
交付場所に受け取りに行った際、マイナンバーカードの暗証番号を登録します。
暗証番号は4つ決めます。
- 署名用電子証明書 英大文字+数字の組み合わせ、6~16桁
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 住民基本台帳(数字4桁)
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
ただし、2~4は同じでもOKとの事です。
また、その場で慌てて決めて、あとでもっと違うのにすれば良かったと後悔しないよう、事前に考えて決めておきましょう。
もちろん、わからなくならないようにちゃんと覚えておくか、メモして他人がわからないように保管しておくなどする必要があります。
マイナンバーカードについて区役所に質問した事とその回答
私が住んでいる西区役所の区民生活課に、疑問点をTEL確認してみました。
引越しや紛失しても、新たに申請書を貰えば、QRコードでの申請も出来ますか?
質問と違う事を答えられてしまう。
再度聞き直したが、またも質問と違う内容の回答。
よく把握していないと様子。調べてくれる様子もない(汗)
受け取りの際に登録する暗証番号の変更は出来ますか?
区役所の窓口で変更できるとの事。
以上、一応TELして教えてもらった事ですが、保証は出来ませんので。ご参考までにとどめておいてください。
マイナンバーカードの疑問あれこれ
現時点で私が思いついた気になりそうな事や疑問点などを挙げておきます。
就職したらマイナンバーを教えてくれと言われた
平成28年1月から、雇用保険や源泉徴収でマイナンバーが必要になっています。
パートやアルバイトも含む全従業員のマイナンバーを取得する事になっています。
そのため現在、就職した場合は会社からマイナンバーの確認を求められる可能性が高いです。
これは法律で決まっている事なので、マイナンバーを求められても不安に思わなくて大丈夫でしょう。
銀行や証券会社に口座を作る場合も、今後マイナンバーを求められる方向になっていくと思います。
住民基本台帳カードは同じような物?
住民基本台帳カードは同じような物ですが、平成28年1月以降は、住民基本台帳カードの発行や更新は出来なくなっている様です。
マイナンバーカードが住民基本台帳カードの後継の様な感じですね。
ただ、両方を所有することは出来ない物です。
お持ちの住民基本台帳カードの有効期限が残っていれば使えます。
マイナンバーカードを交付した際、回収となるそうです。
まとめ
流れをおさらいします。
- 申請する
- 1か月ほど待つ
- 交付通知ハガキが届く
- 必要な物を持って交付場所へ本人が行く
- 交付場所で暗証番号を登録し、マイナンバーカードを受け取る
申請方法は以下の4つ
- 郵送
- パソコンかスマホでインターネットから
- スマホでQRコードで
- スピード写真機でQRコードで
必要な物
- マイナンバー通知カード
- 本人確認書類
- 交付通知書(申請したら送られてくる。最終的にマイナンバーカードを受け取る時に必要)
注意点
申請書を紛失、または引っ越したら、インターネット申請するためにはお住まいの区役所に申請書を貰いにいく必要がある。
郵送の申請は、インターネットからダウンロードして印刷すればOK。
以上、マイナンバーカードの申請について結構詳しくまとめてみました!
新たな情報があれば随時追加していく予定です。
ご参考になれば幸いです。
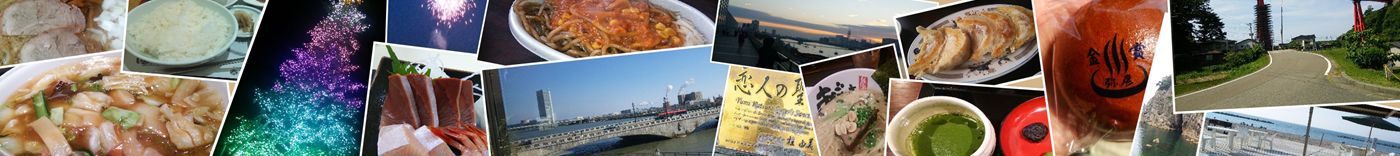




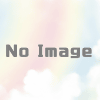









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません